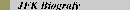
第六章 魚雷艇PT109(上)
南太平洋ソロモン海域、ガタルカナル島の西北方。ブーゲンビル島に展開するアメリカ海軍の魚雷艇部隊に所属していたレッド・フェイは、故国の妹宛に次のような手紙を送った。フェィは、ジャックと同じアイリッシュ系のカソリック教徒であったが、ジャックの死よりも、ジョージ・ロスの死を残念がっている、「昨夜、ジョージ・ロスが死にました。ロスは大義の追求者として誰よりも純粋で強い男でした。駐英大使の息子でジョン・ケネディという艇長も命を落としました。彼は国家の最優秀分子が戦争で死んでいくことを、残酷だとは非難できぬと言っていた士官でした。」1943年8月のことである。
アメリカがニューギニア方面で攻勢に転じたのは、この年の1月のことであった。日本軍はガタルカナル島からの撤退作戦を開始し、連合艦隊司令長官
山本五十六がソロモン沖で戦死したのは4月18日。同海域の完全制圧を狙うアメリカの作戦が続けられていた時期にあたる。
魚雷艇部隊本隊では、ケネディ中尉と、もう一人の士官ジョージ・ロスをふくめて、PT109号艇の乗組員13名のための盛大な葬式を出した。PT109の撃沈が信じられていた数日後のことであったが、その葬儀は本隊の早とちりであった。この葬式事件のちょうど一年後、雑誌「ニューヨーカー」に掲載された一つの記事がアメリカ国民の注目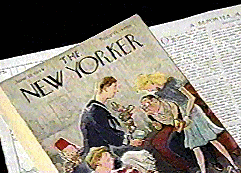 をあびた。筆者はジョン・ハーシー。ハーシー記者は終戦直後訪日して「ヒロシマ」を書いた有名な記者で当時はタイムライフの戦時特派員であった。彼は最初「ライフ」誌の為にこの記事を書いたが、記事が長すぎたため、ニューヨーカー誌に持ち込んだものである。ジョン・フィッツジェラルド・ケネディがヒーローに仕立て上げられた問題の記事である。以下「リーダース・ダイジェスト誌」に転載された要約記事を要旨で紹介する。 をあびた。筆者はジョン・ハーシー。ハーシー記者は終戦直後訪日して「ヒロシマ」を書いた有名な記者で当時はタイムライフの戦時特派員であった。彼は最初「ライフ」誌の為にこの記事を書いたが、記事が長すぎたため、ニューヨーカー誌に持ち込んだものである。ジョン・フィッツジェラルド・ケネディがヒーローに仕立て上げられた問題の記事である。以下「リーダース・ダイジェスト誌」に転載された要約記事を要旨で紹介する。
星の無い闇夜であった。ジョン・F・ケネディ中尉を艇長とする魚雷艇PT109は、ソロモン群島沖の真っ只中、ブランケット海峡にさしかかった。午前2時30分頃のことであった。ケネディ中尉が操縦蛇を握り、ジョージ・ロスが艇尾で双眼鏡を眼にあてていた。艇が角度を転じて暗闇の中に進んだときであった、艇首の機関銃座にいた水兵が叫び声を上げた。
「右二時の位置に敵艦見ゆ ! 」
ケネディは水兵が指摘した敵の艦影を発見したのでただちに同方向に舵を切った、攻撃態勢をとったのである。だが、この時PT109は、空からの敵航空機の偵察を警戒して音を消すために三基のエンジンのうち二基を止めていたのでスピードは出なかった。敵艦影は、日本の駆逐艦「天霧」と判明した。天霧は40ノットの速力で、PT109号艇めがけて突進してきた。体当たりであった。ケネディの魚雷艇は真っ二つに引き裂かれた。あっという間の出来事であった。
ケネディは「やられた。死ぬぞ」と思った、次の瞬間、彼は甲板上に仰向けに打ちのめされていた、マクマホンという水兵はひどい火傷を受けていた。艇が二つに裂けて、艇の後半部は沈み、かろうじて、前部の片方だけが残って浮いていた。ガスタンクから猛烈な炎が噴き出していた。マクマホンは両手を顔 に当てたまま死を待つほかなかったのだが、大波が彼の身体を海中にさらってくれたので助かった。機関手のジョンソンは甲板で眠っていたところを襲われた。衝撃のために艇が裂けたので破片がジョンソンの身体に降り注いだ、彼は肋骨をしたたか打ったが、気が付いた時には敵駆逐艦は闇夜の中に消え去っていた。 に当てたまま死を待つほかなかったのだが、大波が彼の身体を海中にさらってくれたので助かった。機関手のジョンソンは甲板で眠っていたところを襲われた。衝撃のために艇が裂けたので破片がジョンソンの身体に降り注いだ、彼は肋骨をしたたか打ったが、気が付いた時には敵駆逐艦は闇夜の中に消え去っていた。
あたりは、恐ろしいほどの静寂で、あたり一面メラメラと燃え盛るガソリンの音だけが聞こえていた。ケネディが叫んだ。「オーイ。艇上に誰と誰がいるかあ?」マックギアー、アルバート、ソームの三人が弱々しい声で応答した。続いて、海上からも一人ずつ、つぎつぎと生存者が応答した。海中に放り出された水兵達は泳いでいた。PT109号の艇員はケネディ中尉以下13名であったが。二名だけが応答が無かった。即死であった。カークゼイとマーネイの二名であった。「ケネディさん、ケネディさん、助けてやってくれ!マクマホンがひどい火傷を受けています!」ハリス機関手が叫んでいた。見ると100ヤード(90メートル)ほど離れた海上にマクマホンのからだが浮いていた。ケネディは海中に飛び込んだ。ハーバード大学時代、フットボールで背中をやられたので、水泳ティームを作った彼は、泳ぎには自信があった。彼は瀕死のマクマホンをつかまえた。軍服の襟首をつかんで艇に引っ張って返した。艇といってもいまや二つに引き裂かれた材木に過ぎなかったが・・・・。風が出てきた。海中に放り出された水兵は、みるみる内に流され出していた。だが、ケネディは海中に飛び込み次々と水兵を引き上げにかかった。45分位の救出作業であった。ハリスはひどく脚をやられていた、「もうダメだ!」と彼は泣き声をだした。この男はボストン生まれであった。ケネディは「しっかりしろ、ハリス!ボストン男の見せ場じゃないか!」と励ました。
かくしてケネディは海上から全員を艇上に収容したが、水兵達は精神的な衝撃と肉体的な疲労のためぐったりしてすぐに深い眠りに陥ったものもあった。眠らなかった男達は、互いに抱きあって、生き延びることができた奇跡を喜び合っていた。東北方の海上にほのかな灯かりが見えた。「おい、あの灯かりはコロンバンガラ島らしいぞ!」「そうだ。しかし、あそこには、ジャップが一万人はいるわ」西方がヴェラ・ラヴェラ島だと解った時、水兵達は言った。「あそこには、もっとジャップがいる。これで、万事窮すだ!」と、希望は絶たれたようであった。1マイル(1.6キロ)ほど南のギゾ島にある日本軍キャンプの灯かりも見え出した。材木と化した艇は漂流しはじめていたのである。ケネディは「立っちゃいけない。伏せろ」と命令した。立っていると、空に影が反映してその影が動くので、島の日本兵から発見される危険があった。艇はしだいに沈み出したので伏せているスペースも無くなりだした。ケネディは火傷したマクマホンが激しく咳こみだしたので、静かに寝かせて死なせてやる場所を探した。そこで、全員を海中に飛び込ませて、マクマホンの為に小さな死に場所を作ってやった。「どこか小さな島まで泳ぐんだ!」とケネディは全員を叱咤激励した。南東3マイル(4.8キロ)まで泳げば、その海域には、日本軍がいない島が必ずあると思ったのである。ケネディは、天霧に体当たりの直撃を受けた時、その衝撃で飛び散った材木をかき集めて救命艇がわりにした。それに靴を結び付けた、幸い、救命ジャケットを着ていた者が多かった。ケネディは照明用のランターンを救命ジャケットに結びつけ、そしてマクマホンの体に結び付けた命綱の端を自分の口にくわえて泳ぐことにした。ケネディは命綱を強く噛んでいたため、大量の海水が歯の間から入り、かなりの量の海水を飲んでしまった。
5時間の”遠泳”は苦しかったがやっと小さな島に泳ぎ着いた。後で計算してみると、実際に泳いだ距離は、事故発生現場からわずか数百ヤードの距離でしかなかったのだが、天霧に衝突されてから15時間半の時間を海上で漂流していた為であった、ケネディは負傷者を叱咤しながら必死に泳いだ。小島にたどり着くと、さすがに、ケネディも参っていた。渚の浜辺に長々と伸びてしまった。ケネディは激しく嘔吐した。が、ここで彼は考えた。「我が本隊は、ここ数日間、ファーガソン海峡で敵を追ってきたのだ。まだあの作戦は続いているにちがいない。とすると、必ず友軍のパトロール艇がファーガソン海峡を通過してくるはずだ。海峡はこの先にある。」ケネディはパンツを脱いだ。しっかりとランターンを救命ジャケットに結び付けた。「僕は、ファーガソン海峡まで泳いで行ってみようと思う。いいか、僕がランターンを二回点火したらそれが友軍のボートを発見した合図だ。合い言葉は、呼びかけがロジャーだ。返事はウイルコだ。わかったな、ついてこいよ。はぐれて溺れるな!」海峡といっても狭い水路であった。水路ちかくには目的の島影が見えていた。一時間力泳した。小島の海辺にたどりついた時はいつのまにか日が暮れかけていた。ケネディが振り返ったとき、後方に部下は誰もいなかった。「ロジャー!ロジャー!」とケネディが呼んだので、遅れて続いていた水兵たちは、てっきり、艇長が友軍を発見したと思ったのだが、それは間違いであった。
翌日も友軍のボートを探し続けたが徒労に終わった。水兵たちはすっかり絶望していたケネディは叱咤した。夜になると空気は急に冷えこみ濡れた体には寒い夜で、ケネディも全身に悪寒を感じたがそのまま深い眠りに落ちていった。
眼をさますと、また泳ぎ回ることにしたが、誰が言い始めたのか、「バラキューダ」が水の下から人間の睾丸を食いにくる、と言い出す水兵もいた。バラキューダには襲われなかったが、珊瑚礁で足や脛を切った。潮流はグルグル回っていたようで、ケネディ達はここでも同じ水域を泳ぎ回っていたことが解った。空腹と疲労が襲い掛かってくると、絶体絶命の絶望感といったものが全員を包み出した。第三日目の夕方6時頃、やっとファーガソン水路を確認できた。別の小島に泳ぎ着いたが、疲れ切って動くことすらできなくなっていた。「ロス、今夜はおまえがやってくれ。」友軍探しはロスに引き継がれたが、この努力も徒労に終わった。島には水がなかったので、気が狂いそうに喉が渇いた、ケネディは水を求めて、また別のもうすこし大きな島まで泳ぐ決意を固めた。南西方向にはほんのりと島影が見えていた。その島に泳ぎ着くと、この島には椰子が生え繁っていた。椰子の実を割ってジュースを飲んだが、くさくて吐き出してしまった。水を求め、敵に発見されることを恐れながら、マクマホンの救命ジャケットにつけた命綱の端を歯で噛んで、また、別の島への力泳が続けられた。部下の水兵たちは、それぞれ材木にしがみついて、艇長にしたがった。マクマホンの火傷の傷は化膿しだしていた。やっと島の浜辺に辿り着くと、激しい雨が降り出した。「木の葉で水をためよう」翌朝、目を覚ましてみると。木の葉は雨水をたたえていたが、見ると、待望の水の中には鳥の糞がいっぱい溜まっていた。糞ったれめ!
一同はこの島を「鳥島」と命名した。 |