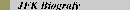
第八章 政界進出
むなしく失われた多くの生命に寄せる深い悲しみとともに、戦争がジャックに残したものは、将来そのような浪費を防ごうという強烈な関心であった。1945年4月、除隊したジャックはハースト系のINS通信社(UP通信社と合併後UPI通信社となる。当時AP・UPと共に米国三大通信社の一つであった)に特別記者として入社、1945年7月、国際連合の設立(国連憲章起草創立総会)を見守るために、サンフランシスコに行った。暴力や死のうずくような記憶も新しい若き戦争経験者にとって、それはある意味で夢の中をさまようような苦い経験であった。しかし政治学の学徒にとっては、絶対に必要な勉強でもあった。「怒りをこめた手紙を君に書き送るのはいともたやすいことだ」ジャックは、この会議に関するジャックの意見を求めたPTボート時代の友人に答えている。「この戦いが、われわれにどれだけのものを失わせたかを思う時・・この戦いで戦死した幾千、幾百万もの人々のことを思う時・・私ばかりではなく、戦争に行った誰もが見たあの勇敢な行為のことを思う時、がっかりしたり、また幾分欺かれた気持ちになるのは、当たり前のことであろう。」続けてジャックは、この会議は道徳的力に欠け、理想ではなく私利私欲だけが諸国家を集合させたのだと言っている。「君は、犠牲が日常茶飯事となっていた戦場を、自分の目で見てきている。そういう犠牲を、サンフランシスコに集まった各国の臆病さ、利己主義と比べるとき、幻滅を感じるのは当然なのだ」
しかしそれ以上のものを、会議に望むのが、もともと無理だったのではないだろうか。各国ともに国際機構にその主権をゆだねる用意がなかったというのが、冷たい現実だったからである。ジャックは、もう一人の若い戦争経験者で、世界連邦を起こそうと考えているコード・メイヤーの世界政府論に熱心に耳を傾けた。「確かに皆が共に法に従う世界政府というものが、解決にはなるだろう。」とジャックはノートに走り書きした。「だが、事実はそのように容易ではない。戦争は絶対悪であるという感情、しかも各国を結びつけるに足りる強いその感情がもしなければ、この国際主義計画はうまくいかないであろう」「物事は上から強制されてもだめだ。」とジャックはPTボートに友人に言っている。
「国家主権の国際的放棄は、民衆から沸き上がるものでなくてはならないであろう。それは、もし選ばれた代表がそうしなかったなら、職を追われるほど強硬なものでなければならないであろう。われわれはつぎの事実を直視しなければならない。すなはち。もう一度戦争になるくらいならばどんな事になってもよいというほど、まだ民衆は戦争を恐れてはいないのである。良心的な反戦論者が、軍人達が今享受していると同じような名声と威信を得ることのできる遠い将来まで、戦争は依然として絶えることはないであろう。」
これらのことが、「君がサンフランシスコ会議のことを考える時に、考えなければならない問題である。君はその成果を、その可能性に照らして判断しなければならない。戦争を幾分なりとも起こし難いものにしたということが、この会議の成果なのだ」ジャックは、いままさに生まれようとしている国連に対する自分の考えを、ノートに次のようにまとめている。
宣伝のしすぎは危険。
期待しすぎてはならぬ。
本当に正しい解決でも、各国に幾分の失望を残すであろう。
結局、万能薬はない。
期待しすぎは禁物、万能薬はない。これが戦争直後のジャックの心理状態であったのである。もともと、ジャックは著述家になりたいと思っていた。だが、サンフランシスコでの体験が、報道陣と一緒に外で待っているより、会議の席に座るほうがよいと思わせたのかもしれない。兄ジョーが死んだこともまた事態を変えた。ケネディ家の人々は1940年の民主党大会の代議員として政界にデビューしたジョーが、一族を代表して政治に進出する人間だと考えていた。のちに作られた神話と違って、父ジョセフが当時まことに悲しくも空席となってしまったすきまを埋めるために、自動的に二番目の息子を待ってきた訳ではない。(勿論、重要な要因の一つであったことは事実であろうし、ジョセフの性格上否定は出来ないが、その事が統べてではないと考える。)多くの若き戦争体験者と同じように、ジャックはあれほど多くの友達が命を捧げた世界の為に、何か役立つことをしたいと感じたのである。たぶん、世界を救う手段としてよりも、むしろ世界がこれ以上に悪化するのを防ぐ手段として、政治というものがジャックを引き付けたのであろうと思う。1946年ジャックは政界の空気を調べるためにボストンに帰った。
ボストンに帰ったジャックは、いわゆるカルチャーショックと呼ばれるものを味わったに違いない。ボストンのアイルランド人として生まれたにもかかわらず。彼は一度 もボストンのアイルランド社会に加わったことが無かった。それまでの彼の生活は、故郷から遠く離れたところで行なわれていた。今や第十一選挙区に入ったジャックは、初めて自分の仲間たちの間に戻った、とはいうものの、完全には仲間意識には徹し切れなかった。ジャックはアイルランド人の頑固さや忠実さは好んだが、彼らの持つ反知性的態度には失望した。チャールスタウンからノースエンドに至る安住宅地帯を選挙運動したジャックは、ケネディ家やフィッツジェラルド家の育った土地の人々と初めて親しく交わった。チャールスタウンの安アパートの薄明かりのホールで、ジャックはデイビット・パワーズに逢った。人並みはずれたやさしさと誠実さを兼ね備えたパワーズは尽きることの無い噂話やアイルランド系ボストン人についての知識や、人をくつろがせる能力でジャックをもてなしてくれた。初めは堅くなってはにかんでいたジャックも、まもなくくつろぎ始めた。しかし彼は最後まで「街の人気者」的態度を身につけることは出来なかった。それでもジャックは人種のるつぼのボストンの街のあらゆる社会に積極的に入り込もうと努力した、その結果ついにジャックは現職の共和党連邦下院議員ラーリー候補を圧倒的な票差でやぶり、ついにその政治家としてのスタートをボストンの街でスタートさせたのである。1946年秋・・ジャック29歳の時であった。 もボストンのアイルランド社会に加わったことが無かった。それまでの彼の生活は、故郷から遠く離れたところで行なわれていた。今や第十一選挙区に入ったジャックは、初めて自分の仲間たちの間に戻った、とはいうものの、完全には仲間意識には徹し切れなかった。ジャックはアイルランド人の頑固さや忠実さは好んだが、彼らの持つ反知性的態度には失望した。チャールスタウンからノースエンドに至る安住宅地帯を選挙運動したジャックは、ケネディ家やフィッツジェラルド家の育った土地の人々と初めて親しく交わった。チャールスタウンの安アパートの薄明かりのホールで、ジャックはデイビット・パワーズに逢った。人並みはずれたやさしさと誠実さを兼ね備えたパワーズは尽きることの無い噂話やアイルランド系ボストン人についての知識や、人をくつろがせる能力でジャックをもてなしてくれた。初めは堅くなってはにかんでいたジャックも、まもなくくつろぎ始めた。しかし彼は最後まで「街の人気者」的態度を身につけることは出来なかった。それでもジャックは人種のるつぼのボストンの街のあらゆる社会に積極的に入り込もうと努力した、その結果ついにジャックは現職の共和党連邦下院議員ラーリー候補を圧倒的な票差でやぶり、ついにその政治家としてのスタートをボストンの街でスタートさせたのである。1946年秋・・ジャック29歳の時であった。
連邦下院議員二期目の1949年のことであった、来るべき1952年の大統領選挙を控えたケネディ(以降、ジャックの表現はやめてケネディと書くことにする。特に記載しない場合はケネディはJFKを意味する)にひとつの岐路が見えてきた。ケネディにボストン市長への立候補の話が持ち上がったのである。周辺の人々からも熱心に勧められた。その時ケネディはこう答えた「私はこの下院での仕事に興味を持っている。ここで出来る仕事が沢山あるように思う」と答えている。もちろん、市長職につきものの落とし穴を避けたケネディは賢明であった。しかし一方、彼がいつまでも下院にとどまるつもりの無いことがハッキリし始めた。1950年までには、ケネディは週末ごとにマサチュセッツに帰り、自分の選挙区から離れた各地で演説をしていた。彼は明らかに1952年の上院議員選挙、あるいは州知事選挙に出馬する準備をしていたのである。ケネディがそのどちらに出るのかは、現職の州知事ポール・デヴァーが再選を狙うか、あるいは現職の上院議員ヘンリー・キャボット・ロッジJrに挑戦するかにかかっていた。ケネディが上院議員のほうを望んでいるのは明らかであった、ある時、ケネディは州議会の建物を指さしながらこういった。「あの角のオフィスで、下水道の契約を取り決めている自分を想像すると、ぞっとするよ。」1952年のはじめイリノイ州の上院議員で、若き下院議員ケネディを父親のような愛情で眺めていたポール・ダグラスと昼食を共にした時のことである。ダグラスはケネディにこう忠告した。「上院議員を狙う のは危険だ。特に共和党がアイゼンハワーを指名した場合はなおさらそうだ、なぜ下院に留まって先任者特権を積まないのか?州知事のほうがまだしも良いのではないか?」ケネディは静かに耳を傾け、ほとんど口を挟まなかったという。疑いなく彼はこの種の忠告を多く受けていた。しかしまるで時間の余裕がないと考えているかのように、ケネディはずっと前から決心を固めていたのだった。1952年4月デヴァーが再び州知事選挙に出馬することを表明すると同時にケネディは上院議員立候補の声明を発表したのであった。そして祖父時代からの宿命のライバル、ヘンリー・ロッジの息子で現職の上院議員であったヘンリー・ロッジJrを七万票の差をつけて破ったのである。勝利は再びケネディを少数党たる民主党最年少上院議員としてワシントンに送り出したのである。 のは危険だ。特に共和党がアイゼンハワーを指名した場合はなおさらそうだ、なぜ下院に留まって先任者特権を積まないのか?州知事のほうがまだしも良いのではないか?」ケネディは静かに耳を傾け、ほとんど口を挟まなかったという。疑いなく彼はこの種の忠告を多く受けていた。しかしまるで時間の余裕がないと考えているかのように、ケネディはずっと前から決心を固めていたのだった。1952年4月デヴァーが再び州知事選挙に出馬することを表明すると同時にケネディは上院議員立候補の声明を発表したのであった。そして祖父時代からの宿命のライバル、ヘンリー・ロッジの息子で現職の上院議員であったヘンリー・ロッジJrを七万票の差をつけて破ったのである。勝利は再びケネディを少数党たる民主党最年少上院議員としてワシントンに送り出したのである。
戦争の経験も彼を鍛えたが、政治はさらに輪をかけてケネディを鍛えた。マサチュセッツ州民主党は普通の意味での政党ではなかった。言ってみればそれは、地方ボスに操られ、無気力な党州委員会に統括されているライバル同士の種々な結社の集まりに過ぎなかった。しかし、ケネディは自らの勢力範囲を開拓し、自らの目標を追及した。こうして彼は、決然とした、たゆみのない不敵な態度で、相手の地元で相手と真っ向から戦って「政治屋」を破りうることを示したのである。 |