|
第十五章 大統領 ウエスト・バージニアの予備選の最中に起きたU2機撃墜事件を発端とする東西冷戦のぶり返しと緊張の激化は、当初ケネディに意外なマイナス効果を追加した。それは、民主党内では、スティーブンソンとジョンソンにプラスした。「戦争が起きるかもしれない時期に、あのような未経験の若造に国は任せられない。それにこんな時期では、経験豊かなニクソンには対抗できない。」と言う意見であった。そしてこの声は現実に共和党ニクソン候補に有利に働いたのである。なぜなら、ニクソンは現職の副大統領であったし、CIAや国務省の政治的機密事項を扱い得た立場から、事態の真相を知りうる側に立つ事が出来たからであった。がしかし・・・、そう思われたのは当初の客観的批評家の観測だけで、時局の真相に近ずき得なかったケネディ側が、かえって知り得なかったがゆえに、日々ささいな個々の局面にとらわれる事無く、政策を立て得たと言うまったく皮肉な結果を招いていたことが、後になって判明してくるのである。それが歴史の現実なのかも知れない。 アイゼンハワー政権は、フルシチョフの攻勢に必死の防戦を試みたがフルシチョフのほうがはるかに巧妙であった。アイゼンハワーは疲れ過ぎていた。誰もアイクの弁明には耳をかそうとしなかった、大義はソ連にあり非はまさにアメリカに有り過ぎたのである。風向きは、やがてケネディに吹き始めた。弱り目に祟り目の現政権、つまり、現政権の副大統領であるニクソンを攻撃することのできる絶好の材料を、フルシチョフが提供してくれた形となってしまったのである。まさにフルシチョフの援軍であった。 ケネディは民主党民主党全国大会へ駒を進めた。
 二つの天王山を乗り越えて順風満帆の予備選挙を進め、ロサンゼルスの全国大会に乗り込んだケネディが、圧倒的に、しかも文句なく第一回の投票で指名されたと言っても、もはや意外性も何もなかった。が、しかし予備選の最終盤にきて、最後にしのぎを削りあったジョンソンを、ケネディが副大統領に指名した時、アメリカ中の有権者がびっくり仰天した。南北の結合、新旧キリスト教の融和と、大義名分はいくらでもあったが、なんとも理解に苦しむケネディ・ジョンソンの握手であった。(詳細は”ケネディ対ジョンソン”の項目参照) 二つの天王山を乗り越えて順風満帆の予備選挙を進め、ロサンゼルスの全国大会に乗り込んだケネディが、圧倒的に、しかも文句なく第一回の投票で指名されたと言っても、もはや意外性も何もなかった。が、しかし予備選の最終盤にきて、最後にしのぎを削りあったジョンソンを、ケネディが副大統領に指名した時、アメリカ中の有権者がびっくり仰天した。南北の結合、新旧キリスト教の融和と、大義名分はいくらでもあったが、なんとも理解に苦しむケネディ・ジョンソンの握手であった。(詳細は”ケネディ対ジョンソン”の項目参照)一方、ニクソンはシカゴで行われた共和党全国大会で、ほとんど満場一致の状態で共和党大統領候補に指名されていた。そして、ニクソンが指名した副大統領候補がなんとケネディと同郷で、しかも母方祖父のハニー・フィッツジェラルド以来フィツジェラルド家・ケネディ家連合の政敵、ロッジ家の血を引くヘンリー・キャボット・ロッジ Jr であった。アイリッシュ移民の末裔に対して、ニクソンは同じボストンのヤンキーの名門の出をぶつけてきたのであった。  1960年11月のワシントンは例年になく寒い冬が早く訪れた。11月8日に行われた大統領選挙の結果は、ケネディにとって誠に不本意なもので終わった。全国の投票総数六千八百八十三万八千五百六十五票中、ケネディとニクソンの差はわずかに十一万二千八百八十一票であった。史上最接近差を記録した、文字通りの「間髪の差」であった。ニューヨークタイムズは、開票日翌日の朝刊を「ケネディ当選」で、ワシントンポストは「当落不明」で朝刊のトップを書いた。ケネディが勝ったのか、負けたのか?それともニクソンか?ワシントンの読者を戸惑わせるに十分なほどの僅差であった。ニクソンは「敗北宣言」を最後の最後まで出し渋ったと言う。ニューヨークや東部諸州はケネディの地滑り的圧勝であったが、開票が西に進むにしたがって、ニクソンがぐんぐんと盛り返してきたのである。アメリカの西と東の違いがはっきりと開票結果に現れて、西部の大州カリフォルニアがあぶないと聞いたときには、さすがのケネディもため息をついて、側近に当たり散らした。「作戦の誤りだ!」ケネディが夏の民主党全国大会の指名受諾演説の中で明らかにした「ニュー・フロンティア」(詳細は”ニュー・フロンティア精神”の項目参照)と言う新しいキャッチフレーズが、皮肉な響きをもって聞こえさえした。全国大会のために用意されたニュー・フロンティア演説がニクソンのために、東から西に進むほど無残に裏切られていった開票結果は、それがたとえアメリカの矛盾であったにせよ、偏見であったにせよ、それはケネディにとっては大きな衝撃で 1960年11月のワシントンは例年になく寒い冬が早く訪れた。11月8日に行われた大統領選挙の結果は、ケネディにとって誠に不本意なもので終わった。全国の投票総数六千八百八十三万八千五百六十五票中、ケネディとニクソンの差はわずかに十一万二千八百八十一票であった。史上最接近差を記録した、文字通りの「間髪の差」であった。ニューヨークタイムズは、開票日翌日の朝刊を「ケネディ当選」で、ワシントンポストは「当落不明」で朝刊のトップを書いた。ケネディが勝ったのか、負けたのか?それともニクソンか?ワシントンの読者を戸惑わせるに十分なほどの僅差であった。ニクソンは「敗北宣言」を最後の最後まで出し渋ったと言う。ニューヨークや東部諸州はケネディの地滑り的圧勝であったが、開票が西に進むにしたがって、ニクソンがぐんぐんと盛り返してきたのである。アメリカの西と東の違いがはっきりと開票結果に現れて、西部の大州カリフォルニアがあぶないと聞いたときには、さすがのケネディもため息をついて、側近に当たり散らした。「作戦の誤りだ!」ケネディが夏の民主党全国大会の指名受諾演説の中で明らかにした「ニュー・フロンティア」(詳細は”ニュー・フロンティア精神”の項目参照)と言う新しいキャッチフレーズが、皮肉な響きをもって聞こえさえした。全国大会のために用意されたニュー・フロンティア演説がニクソンのために、東から西に進むほど無残に裏切られていった開票結果は、それがたとえアメリカの矛盾であったにせよ、偏見であったにせよ、それはケネディにとっては大きな衝撃で あった。このような僅少差で勝った場合は、国民の圧倒的な支持を得て選ばれた大統領ではなかったのだから、国民の半数近くに拒否された大統領として、あまり勝手な事は出来ないというアメリカ政治の暗黙のルールをケネディはよく知っていたのである。 あった。このような僅少差で勝った場合は、国民の圧倒的な支持を得て選ばれた大統領ではなかったのだから、国民の半数近くに拒否された大統領として、あまり勝手な事は出来ないというアメリカ政治の暗黙のルールをケネディはよく知っていたのである。1961年1月20日のワシントンは快晴の天気であった。しかし前日までは雪が降り続き、第35代アメリカ合衆国大統領の就任式は延期が噂されるような状態であった。しかし、東の空に昇った1月20日の太陽は、燦々と陽光をさし、雪を溶かしていった。議事堂広場の東正面に特設された大統領就任式場の中央スタンドは、矢の束とオリーブの枝を掴んだ鷲のマークの金色の大統領紋章が、真っ白のペンキの中に美しく描き出されて象徴的であった。・・・この荒鷲は、力の矢を掴んで平和のオリーブの枝をなげるのである。・・・・・ 定刻前、ジャクリーヌ夫人が議事堂の中から姿を現した。その姿はフランス人形のように美しかった。淡いたん色のミンクの襟付きコートを着て、円筒形の同色の帽子をかぶっていた。どっと拍手が沸いた。軍楽隊のマーチにのってジョンソン新副大統領が入場すると、アイゼンハワー大統領がニクソン副大統領に手をとられて壇上の人となった。又、激しい拍手である。史上最年長の大統領であったアイゼンハワーは悠々とジャクリーヌ夫人の横に座った。ワシントン市民は、この負け犬に長い拍手を惜しまなかった。キャン 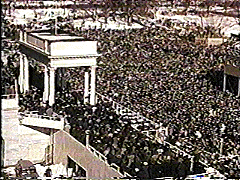 セルされた訪日計画のあと、極東旅行から帰国してきた彼に対して、五十万のワシントン市民が街頭に出て大歓迎陣をひいたお国柄であった。 セルされた訪日計画のあと、極東旅行から帰国してきた彼に対して、五十万のワシントン市民が街頭に出て大歓迎陣をひいたお国柄であった。その三分後。黒いコートを着たケネディ新大統領が、シルクハットを手に持ったままゆっくりと階段をあがった。割れるような拍手の広場をゆっくりと見渡して緊張した表情をほころばせると、アイゼンハワーに会釈して旧大統領の右側の椅子に腰を下ろした。国家が吹奏され式典の幕が開いた。頭巾のような深い黒の帽子をかぶった黒人歌手マリアン・アンダーソンが、しみわたるような美声で国家を歌い終わると、カッシング大司教が祈った。アメリカ大統領の就任式にカソリックの司教が登場したのは初めての事であった。思えばケネディにとっって、ニクソンとの大統領選挙は苦しい宗教戦争であった。その時、演壇から白煙が上がった。儀式の演出か?とだれしもが思ったが、珍事の発生であった。ヒューズの配線故障による発火で消防士まで飛び出す騒ぎになり、式次第は遅れた。八十六歳の感傷派詩人ロバート・フロストはケネディのお気に入りで、ハーバード大学の文学部長を長く勤め、ピュリッツアー賞を四度も受賞した老人である。フロストが「ニュー・フロンティア」の詩を読み上げようとした時、強風が老詩人の手から原稿を吹き飛ばしてしまった。老詩人は怒り出して残った原稿を捨て去り、原稿無しで暗誦し始めた。 「西に向かって漠然と拓いてきた土地に、物語もなく、芸術もなく、広がりもなく、在りし日の祖国は、明日はいかになるか・・・・」  就任の宣誓は四十分の遅れとなった。ウオーレン最高裁長官とケネディが相対して立った。ウオーレンはケネディの祖母メアリー・ヒッキーが愛用したケネディ家に伝わる古びた聖書の上にケネディの左手を置かせて、憲法に従い、大統領の職責を全うする事をケネディに誓わせた。この瞬間、アメリカ合衆国第三十五代大統領が誕生したのである。しかし、この日より三年を経ずして、同じウオーレンがケネディの死の幕引きを勤めることになろうとは、よもや、両者とも夢想だにしなかったであろう。まさに、歴史の皮肉であった。 就任の宣誓は四十分の遅れとなった。ウオーレン最高裁長官とケネディが相対して立った。ウオーレンはケネディの祖母メアリー・ヒッキーが愛用したケネディ家に伝わる古びた聖書の上にケネディの左手を置かせて、憲法に従い、大統領の職責を全うする事をケネディに誓わせた。この瞬間、アメリカ合衆国第三十五代大統領が誕生したのである。しかし、この日より三年を経ずして、同じウオーレンがケネディの死の幕引きを勤めることになろうとは、よもや、両者とも夢想だにしなかったであろう。まさに、歴史の皮肉であった。就任演説が始った。ケネディはオーバーを脱ぎ捨て演壇に立った。半身を開いてかまえ、風が彼の髪を乱すと、それでもう完全にケネディ・スタイルが出来上がっていた。彼は歯切れよく、ロンドン訛りが少し入ったニュー・イングランド調の雄弁さで大聴衆に呼びかけた。「イエス!イヤー!」の大歓声であったが、これはケネディが最も得意とする国民大衆への溶け込み方式とでも言うべき演説スタイルであった。 「友にたいしても敵にたいしても一様に次の言葉を伝え様ではないか。たいまつは新しい世代のアメリカ国民にひきつがれたと。」すべての聴衆が大歓声を持って答えた。会場はニュー・フロンティアの大合唱となった。風は冷たく、身も心も凍結しそうであったが、議事堂広場を埋め尽くした大聴衆は、ケネディの仕掛けた催眠術にかかったようにすっかり陶酔していった。 就任パレードの大ページェントは、午後2時30分から始った。キャデラックのオープンカーの人となった43歳の新大統領と、31歳のファースト・レディは、両側を十重二  十重の人垣に囲まれたペンシルバニア通りを練ってホワイトハウスに向かった。絢爛豪華な大絵巻きであった。13キロの行程を、全長三千七百メートル、三万八千人による空前の大パレードであった。アメリカ五軍によるパレードのなかには、かつてケネディが苦難を共にした「PT109」の同型魚雷艇まで引っ張り出されケネディを喜ばせた。 十重の人垣に囲まれたペンシルバニア通りを練ってホワイトハウスに向かった。絢爛豪華な大絵巻きであった。13キロの行程を、全長三千七百メートル、三万八千人による空前の大パレードであった。アメリカ五軍によるパレードのなかには、かつてケネディが苦難を共にした「PT109」の同型魚雷艇まで引っ張り出されケネディを喜ばせた。この大パレードの途中、ケネディは観覧席の中にひとりの人物を見た、ケネディはオープンカーの上で立ち上がり、手をかざして、その人物に挨拶を送った。父親ジョセフ・パトリック・ケネディ72歳にとってどの様な感慨の一瞬であったのであろうか。 |